企画調査委員会
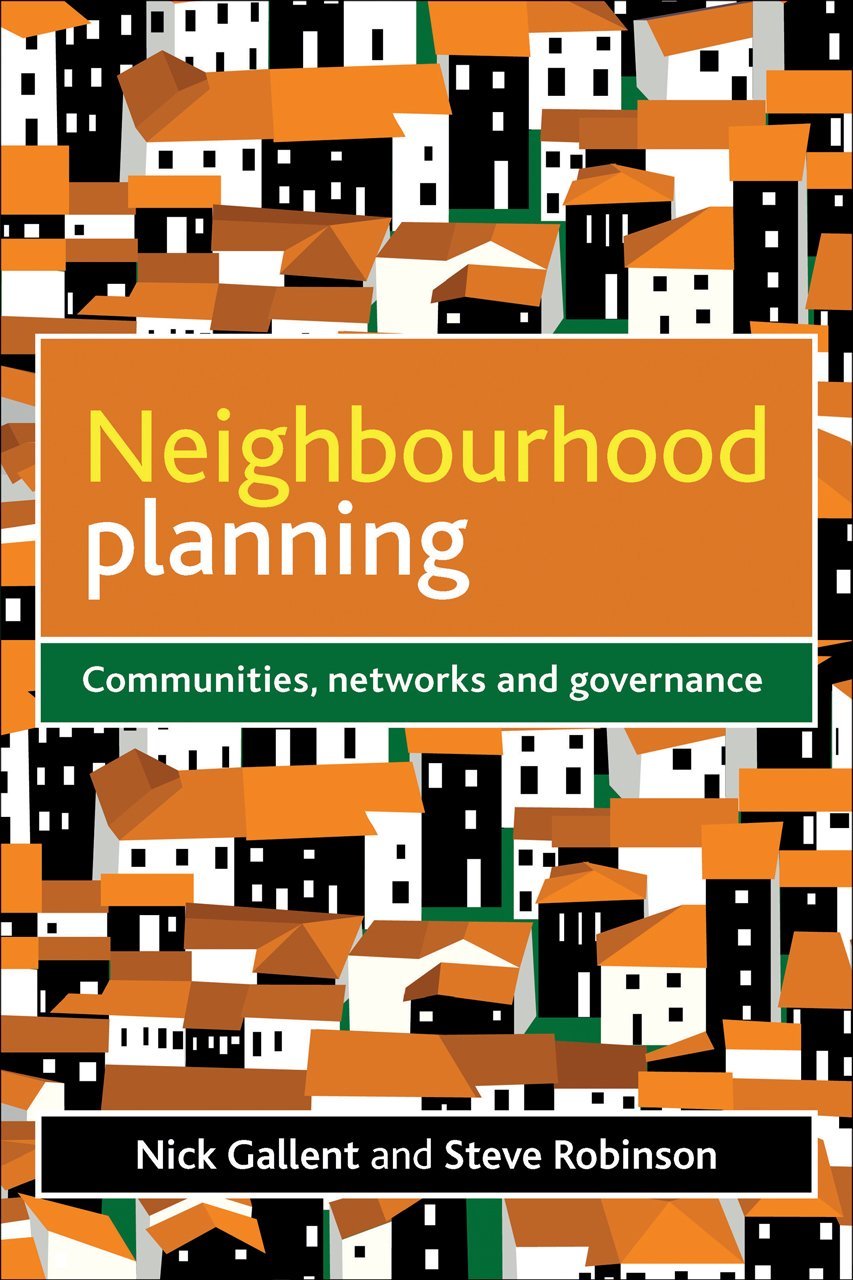
Neighbourhood planning: Communities, networks and governance
Policy Press /2013年
現在,日本各地における計画の現場では「地方分権化」という大義名分の元,「他との調整をしなくてよくなった」というおかしな空気感が広がっている。また,最近の「ローカリズム」というもっともらしい輸入キーワードが,その正当化にさらに拍車をかけていないだろうか。
本書はその「ローカリズム」発祥の本家ともいえる英国での最新の研究書であり,かつわかりやすい解説書である。一読して,如何に日本国内でその概念が誤用されているかということが思い知らされる。「ローカリズム」とは,ローカルエリアが好き勝手な(そしてそれらは往々にして全体を悪い方向に向かわせる)権限を持つということではない。それは,1)ローカルも責任を伴うということ。そして,2)ローカル間もしくは上位機関との縦横のネットワークが今まで以上に重要になるということが,実例を交えて整理されている。書名こそ既に人口に膾炙した用語である「近隣計画」という平凡なタイトルであるが,その根底がこの2断面において大きな地殻変動を起こしていることが解きほぐされている。
また,ここで言うローカルはわが国の地方自治体ともスケールが全く異なる。本書を縦に貫くのは,パリッシュ(parish教会教区)という地域単位である。パリッシュは英国全体でおよそ19,000存在し,単純に人口割りすると平均3,300人程度のスケールとなる。現在まで近隣計画の基本ユニットとされることの多かった小学校区(人口10,000人程度)よりもかなり小さい。日本に当てはめると38,000程度の地域ができることになり,現在の市町村数(1,719)よりも市制町村制施行(明治22年)以前の町村数(71,314)の方がむしろ近い。お互いに顔の見える集落レベルでの計画が,ローカリズムの立脚点といえる。
本書では,その成否を分けるポイントとして,1)ローカルな住民レベルでの生きた意見や活動をどう政策担当者と結び付けるか(connectionという用語が頻出する),2)ローカルで手作りのものでも,その成果をプロの仕事としての水準をどう確保できるか,ということを指摘している。これらを保証するのはまさに「周囲や他主体との関係」としてネットワークがどう機能しているかという点に多くを負うことになる。
なお,本書筆頭著者のNick Gallent氏はカーディフやマンチェスターの大学で研鑽を積み,現在若くしてUniversityCollege Londonのプランニング部門のヘッドとなっている。彼の精力的でヒューマンな研究活動には今後も目が離せない。
紹介:筑波大学教授 谷口守
(都市計画305号 2013年10月25日発行)